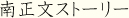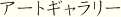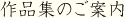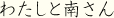小学三年生の春休み、父親の製材所で手伝いをしていた南さんはちょっとした油断から片腕をベルトコンベアーに巻き込まれてしまい、瞬時にそれをとろうと、もう片方の腕もコンベアーに突っ込んでしまった。気がついた時は、病院で両親に見守られていた。両腕は機械にもぎとられあたりは血だらけ、近所の方のトラックですぐに病院に運ばれた。命も危うい状態で、「命は助かっても両腕なしでは...」という医師に「命だけはどうか助けてください。」と両親は土下座をして悲願された。
意識が戻りしばらくたった頃、南少年は付き添う母親にたずねた。「手がかゆいのにかけないねん・・・僕の手どうなってるん...」すると母は、「ちょっと怪我したからな、後ろでしばってあんねん」と。そして治療の時はいつも目隠しをされていた。 ある日いつものように目隠しをされ治療をおこなっている時、南少年は目隠しの隙間から、自分の手がないことを知る。幼いながらもそのショックは相当なものだったと思う。それでも病院では、母や看護婦さんやみんながいてくれて身の回りのことをやってくれていたし不自由さや寂しさを感じることも少なかったという。
一年後、病院を退院し自宅に戻った。トイレもご飯も着替えも自分ひとりではできない。今まで普通にできていたことが何ひとつできない。両親も忙しく、病院にいたころのようにはいかなかった。
外で友達の声がするから一緒に遊びたくて出て行った。「大丈夫か...」そう言ってくれると思っていたのに、「手なしロボット」とからかわれた。悔しくて追いかけるけれど思うようにバランスがとれずに転んでしまう。立ち上がって走っても、またすぐに転んでしまう。南少年の心は傷つき、 だんだんと家にひきこもるようになっていった。
そんな様子を心配して、母親が買物に誘ってくれた。そこでも、「言う事きかんかったらあんな風になるで...」見知らぬ親子の心ない会話が聞こえくる。
「あの時手伝えってゆうたから、こんな事になったんや。お父ちゃんのせいや」「兄ちゃんの手伝う番やったのに...」恨んでも人のせいにしても、何もかわらなかった。惨めで悔しくてつらかった。何にもでない、生きててもしかたない、生きていくのがつらい、、、そんな思いが日に日に強くなり、死ぬことを考えた。
台所で包丁を取り出し足ではさみ、のどを刺そうとした。
でも、両親の悲しむ顔が目に浮かび死ぬこともできなかった。
しばらくして、学校の先生のすすめで養護学校へ転入することになった。学校に行くと決まって、足で字を書く練習を始めた。そうして4月、2年遅れで4年生になった。
養護学校には、いろんな子がいた。そこではみんな助け合い優しかった。友達と過ごすことが楽しく、南少年は少しずつ自分らしさを取り戻していった。
低学年の頃は手をかしてもらうことにも甘えられたけれど、学年があがるにつれてそれも恥かしく思うようになってきた。
学校生活の中でやっぱり一番困ったのは、トイレの問題だった。学校に行く前にトイレをすませ、終わったら一目散に家に帰る。そんな生活が続いたある日、学校の帰りにどうしても我慢ができずに一度だけ失敗をしてしまったことがある。その事が南少年の中でとても悔しく恥かしく、二度と失敗したくないと思った。
どうしたらいいのか...を考えた。思いついたのはできるだけ水分を取らずあまり食べないということ、成長期の男の子が、食べず飲まず過ごすことは大変な我慢があったと思う。それでも、それ以来二度と失敗をすることはなかったという。
この頃ご両親は、南さんが将来家賃収入で食べていけるようにと製材所をたたみその土地にアパートを建て小さな食堂をはじめた。
当時14歳(中学2年生)学校生活にも慣れ将来の事を考える年頃になっていた。
| 目次へ |